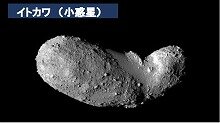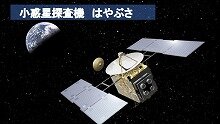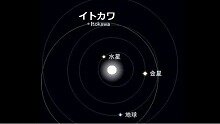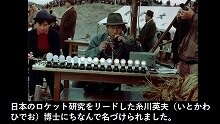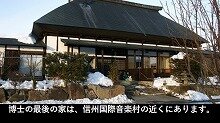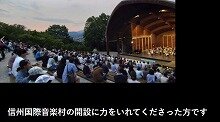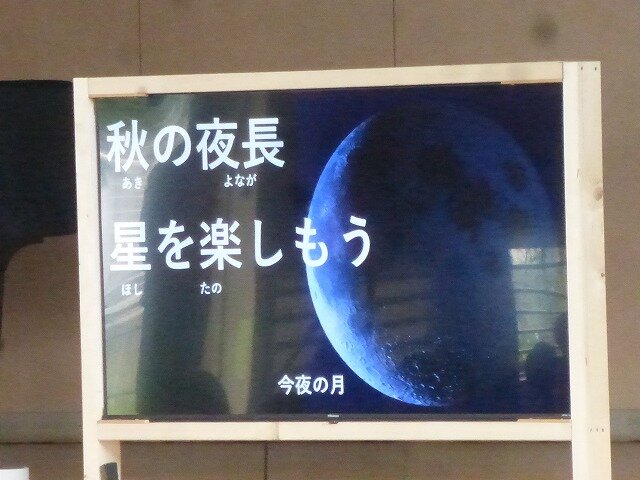2025年9月17日(水) 「月と望遠鏡」日本宇宙開発の父・糸川英夫博士と丸子北小
9月の校長講話「月と望遠鏡」~秋の夜長 星を楽しもう~

9月17日(水)の北小っ子タイムに9月の校長講話が体育館参集で行われました。
今回のお話は「月と望遠鏡~秋の夜長 星を楽しもう~」でした。【以下、話の概要を掲載】


先週の皆既月食を見た人はいますか? 私も夜中に起きて、夜空を見ました。
まぶしい満月の月が徐々に欠けて、 赤茶色に変って様子はとても神秘的でした。
私は小さい頃から車も大好きでしたが、太陽や月や星を見ることも大好きでした。
あまりにも好きすぎて、中学校の時に望遠鏡を作ってみました。これが、その望遠鏡です。
この鏡に光が集まり、大きく見えます。 今は鏡を本体から外してありますので、昇降口の
テレビの前に展示しておきます。 自分の顔がどんなふうに映るか試しに見てください。
丸子北小学校と同じように、私の通っていた中学校にも探究の時間がありました。
しかも100分間の探究の時間でした。3年間、この探究の時間で望遠鏡を作ったり、
望遠鏡で観察をしたりしました。 一番苦労したことは、この望遠鏡の命である、
鏡をどのようにして固定するかで1年間試行錯誤しました。
キズをつけてはいけないし、ネジで微妙な調節をしなければなりません。
ネジ1本をつけるのに、何時間もかかることがありました。
結局、これが一番良い方法だということは見つかりませんでした。
望遠鏡づくりは失敗の連続でした。 でも、なんとかか鏡を固定して、
月や太陽、土星や木星を見た時の感動はいまだに、覚えています。
月の表面のゴツゴツや太陽の黒点、土星の輪、木星の衛星を写真や本でなく、
自分の目で見れた嬉しさはたまりません。また、宇宙の大きさに比べて、
自分はなんてちっぽけなんだ...と思い、小さな悩みなんかどうでもよくなりました。