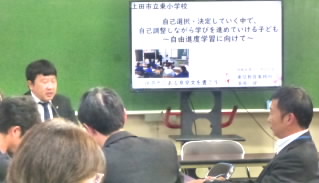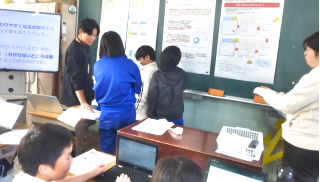2024年11月20日(水) つぶやき147「自由進度学習」への挑戦!
校長の大きなつぶやき147「自由進度学習」への挑戦!
今年度、本校の3つある研究部会の一つ「個別最適な学学習をび部会」では、
子ども一人ひとりが計画を立て、自分のペースや、字Bんに適した学び方で
学習を進めていく「自由進度学習」を通して、「自己選択・自己決定していく
中で、自己調整しながら学びを進めていける子ども」の育成をめざしています。


日頃一般的に行われているのは、一斉学習といって、
教師1人が大勢の子どもたちに対して一斉に授業をするというものです。
この授業形態では、みんなで一斉に同じ課題に取り組み、
みんなで交流し、深め合いながら学習を進めていきます。
それに対して、自由進度学習というのは、子どもたち一人一人が自分のペースで、
教師が用意した手引き(単元計画表)を見ながら自分で学びを進めていきます。
一人ひとりが自分の計画に沿って進めていくため、同じ教室にいながらも、
その時間、取り組んでいる学習内容は異なります。
しかし、最終的には、学ぶこと、つけたい力は同じです。
一人一人が自分のペースで理解できるまで課題に取り組めることが特徴です。


今回、5年生の国語の単元「説得力のある意見文を書こう」の学習を「自由進度学習」
で挑戦し、11月20日(水)には東信教育事務所学校教育課指導主事の参観・助言のもと
この「自由進度学習」の授業公開(全校研究授業)が行われました。
単元としてのねらい(つける力)は
「資料を用いて、『地球温暖化』について、説得力のある意見文を描くことができる」
「自分の考えが詠む人に伝わりやすいように、書き表し方を工夫することができる」
また、本時につけたい国語の力として、「授業づくり構想シート」(指導案)には
6点明記されていますが、「自由進度学習」のため、一人ひとり本時のつけたい力(主眼)
が異なってきます。まさに「指導の個別化」と「学習の個性化」を図りながら、
一人ひとりが学習を自己調整していきながら進めていかなければなりません。